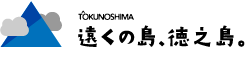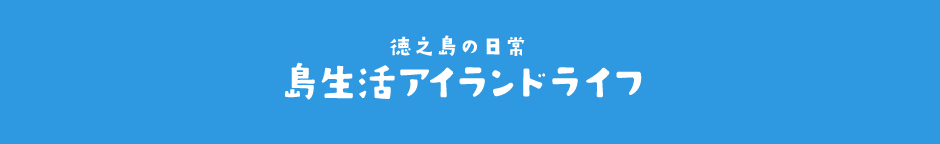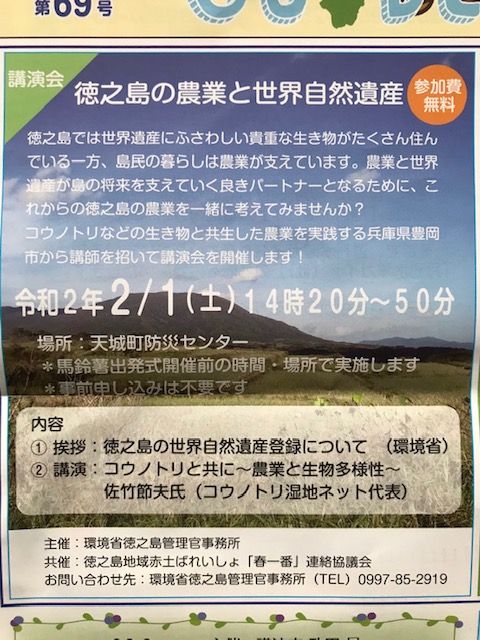アウトドア
島内在住者向け耳より情報
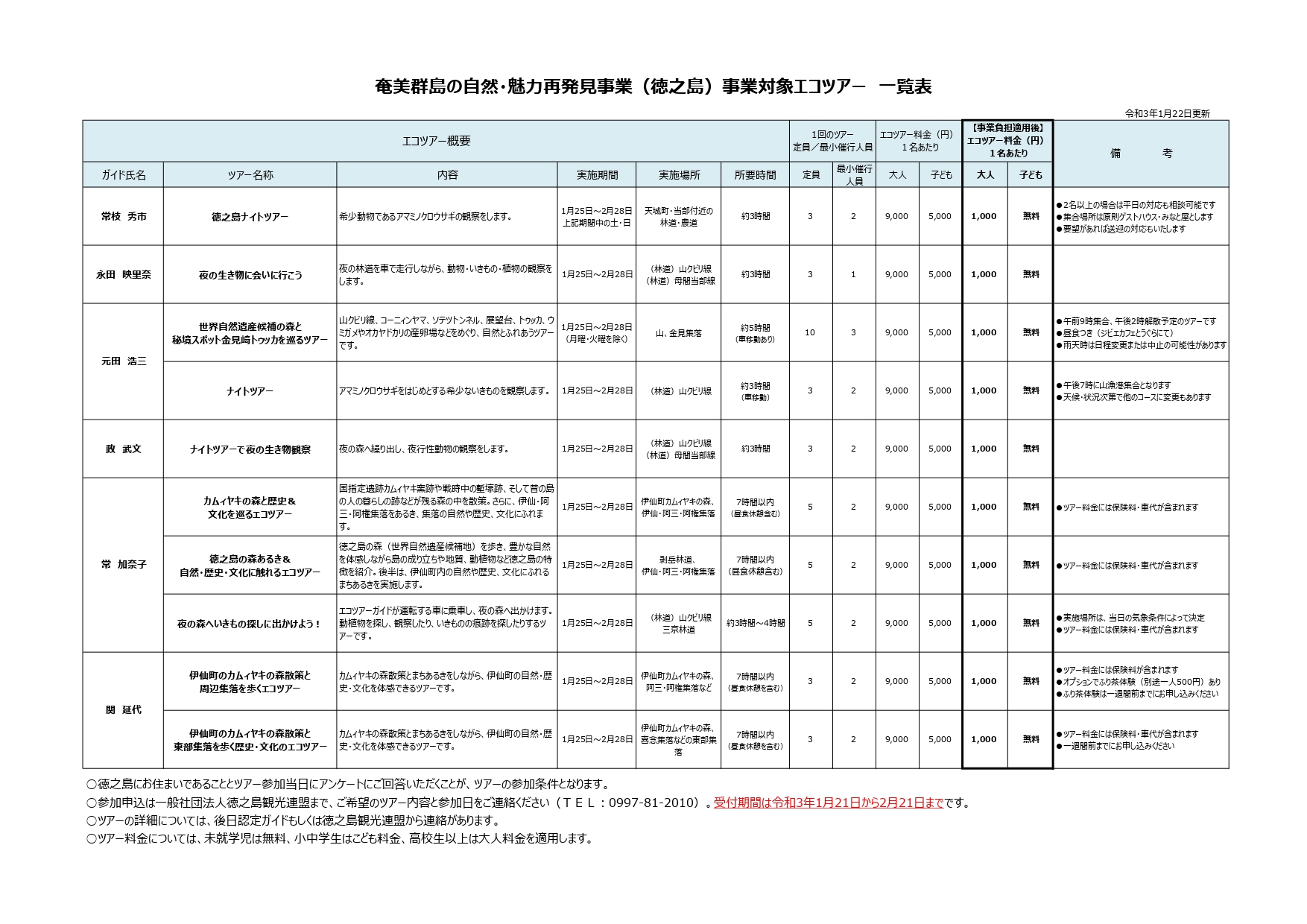
鹿児島県の事業で、島内の在住者がエコガイドさんのツアーを受けた場合に、一律8,000円の補助が出る制度があります。
ラスト・イザリ
いくぶん温かくなってきましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
農繁期で忙しく、なかなか海に行けない。
そんな方も多いのではないでしょうか。
さてさて、かく言う私も、潮の状況等考えると、恐らくラストでありましょうイザリに、せっかくなので行ってきました。
成果です💡

オニハゲブダイ
シマスズメダイ
テナガダコ(シガリ)
でした💡
さすがに終盤になると、タコもアオバチもデカイですね✨
60センチありました😊
しかし彼らが寝ている場所が地表に出るのも終わり、来期のシーズンを楽しみに、私は徐々に釣りモードに持っていけたらと思います✨
でわでわ皆様、良いフィッシングライフを👋✨

私のキッスで魅了してやりました💋
地味?
地味?
きっとそう感じる方の方が多いんでしょうねー
今回は羊歯です羊歯!!
シダと読みます。
だけど今回紹介するシダは一味違います。

こちら‼️
実に美しいシダですね✨
判りませんか?
この美しい姿を。
判らないで結構です。
判らない、興味無いくらいが丁度いいです💨
絶滅危惧種ですからね。
興味持たれないくらいが丁度良いです😊w
種名をホウライハナワラビと言います。
めったに見ることはないですが、見ても分かりにくいかもしれません。
しかし
実に美しいシダなので、今回ご紹介のページを設けさせていただきました😊。
島の生物多様性は、世界の宝と言える価値を持ってると言えます。
その美しい命の輝きを、知っていただければなと👍
冬の夜は楽しい
どうもこんばんは
夜海専門の私です。
今回はやっぱりイザリのネタです。
釣り自体は4月までお休みするかもしれません(^_^;)。
では今回行った(私が普段行くポイントは、いろんな条件が重なり、しばらく行けてませんでした。)イザリの成果です♪

タコ多めです。
まぁ、タコは私大好きなので、嬉しい限り。
ちなみに手のひらサイズ以下は絶対獲りません私。
魚、カニは釣り餌のために(それでもベラ類は死に餌の食い付き悪いので、これも獲りません。)取りますが、あとは人間の餌になる獲物しか獲りません。大きくなって帰ってきたら獲ります✨
伊勢海老ももちろん、夜光貝だって小さいのは見つけても捕らないようにしたいですね💨

二日目はこんな感じ✌
魚もエビもタコもまんべんなく。
良い晩ごはんになりました(^o^)
話変わりますが、個人的な話で、今年私バイク(普通二輪)の免許取ろうと思ってまして、理由は、旅先でレンタカー借りるのと、バイク船に積んで持ってくのだと、2泊以上はバイクの方が安いという事実に気付いたからです。
ちょっと今年は身軽なスキルを手にいれて、いろんなことにチャレンジしてみたいと思いますー👏✨
それでは。
農繁期で忙しい方も多いかと思いますが、楽しく遊ぶ心のゆとり、忘れないでくださいねーーーーーー👋👋👋
森あるき体験
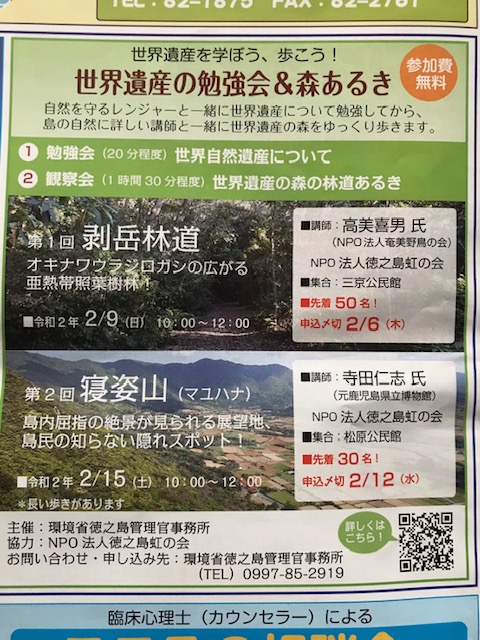
NPO法人虹の会主催にて
2週連続、自然の勉強会と森あるきを開催します。
地元の人が、地元の自然を知るって大切なことですね。
こちらは定員があるので、事前にお申込みした方がいいですね。
みんな違ってみんな良い
さーて、新年あけましたの動植物紹介です💡
徳之島唯一のツチトリモチ属(群島内だと他に、奄美大島にユワンツチトリモチって固有種もいます。)であります、キイレツチトリモチを今回はピックアップ💡
名前の由来は、鹿児島本土の喜入町で初めて見つかったためで、鹿児島県では準絶滅危惧種に指定されています。

なぜ絶滅危惧種になっているかと言うと、やはりそのメンドーな繁殖に由来していると思われます。
一見キノコのようにも見えますが、立派な植物(キノコと植物の違いを知らない人のために一応補足、サンゴとワカメ、人間と鳥くらいの違いがあります。)で、寄生植物(他に、ヤドリギやナンバンギセルがあります。)というジャンルになるのですが、寄生する宿主に生息を依存し、雌雄同株なのは幸いですが、ヤドリギなどと違い、葉緑素を持たないため、自身でエネルギーを生産することができず、種子は発芽後、宿主の根に辿り着けて初めて成長することができるという、極めて哺乳類臭い、いや、人間臭い植物だと言えます。
そんなメンドーな暮らしぶりな彼らにもおそらく何か役割(研究中らしいです)があり、生物多様性の端を担っています。
島の多様な生物層を紐解き、一つ一つ理解していくことで、新しい側面や奥深さを見つけることがあります。
そうやって、日々の島暮らし、充実したものにしていきたいですねー。
そうそう💡 ちょうど今の時期、各地域の林縁にて見掛けることができるので、是非探してみてください🙌
でわでわ。
冬の海の楽しみ方
あけました。
おめでとうございました。
さて、気づけば年越してました。
残念な年末年始を過ごしてました。どうも私、例の人です。
めっきり寒いのと、農繁期と、仕事に追われ、正直、釣り行けてません。
が!!!!
イザリは行きました\(^-^)/w
ってことで、ご存知ない方もいらっしゃるかと思いますので、イザリについて軽く説明。
ざっくり言うと、夜間の寝てる魚を獲る。
です。
詳しく言うと(長い話が苦手な人は帰ってよし!)冬の夜間の最大潮位差を利用した、ショア、サーフ、リーフでの潮干狩りです。ただし、狙える獲物は、二枚貝類だけでなく、サザエや夜光貝などの、基本的に水深を必要とする貝類も地表に出ます。
なぜなら、12月~3月は、マイナス潮位と言います、通常最低潮位となる基準潮位を下回る位置まで、潮位が下がるためです。
これはこの時期の、大潮含む後半の中潮までです。
どのくらい下がるかと言うと、私の知る限りですと、最高でマイナス38センチ下がりました。
高気圧が重なると、もっと下がるかもしれませんが、時期が時期なだけに、高気圧はほぼほぼ大陸上空に鎮座してなかなか南下しません。
なので、奇跡に近いかもしれませんが、マイナス40センチ行きたいですね。
そうそう、私はマイナス10センチ以下まで下がった潮の日に行かれるのをオススメします。
なぜなら

こういった獲物が出るのはマイナス10センチ以下が多いからです。
そして、ここが一番重要だと思いますが、マイナス10センチ以下の潮位は、上がり潮と下がり潮、あびきの差、あびきの回避のしやすさが如実です。
上でも申しましたが、イザリは、最大潮位差を利用した漁法ですので、潮の変わり目から、危険な波まで、シビアに潮を読まなければなりません(島の人だと大袈裟なとか言う人がありますが、その人達は何かあった時に責任取ってくれるわけではありません。)。
まして夜間ですし、面白いように捕れる時だってあります。気付かないウチに、電灯の電池が切れたり、潮に回られて帰れなくなっていた、なんて良くある話です。
大袈裟な、なんて言う人ほど、そうなる確率高いです。
ちょくちょく話てますが、環境は循環を持ってバランスを取っていると話題にします。
人間だけが海の恩恵受けるなんてムシが好すぎるんですよ。その栄養分を陸に上げて、海には返さないなんて、環境がそれを許しません。
海はいつでも、奪えるモノを奪うつもりでそこにあると思ってください。
我々は、その落とし物を、恵みだと言って享受してるに過ぎません。
特に、下げ止まりからの満ち潮は思う以上に早いです。
潮位差が大きいほど、引力と潮の揚力で気圧も不安定になります。
事故に合う人ほど、気象の読みが未熟で、周囲をよく見てません。
天気と大潮だけ見るのは間違い。
必要なのは、潮位差、潮位、干満時間、前24時間と、後4時間の風向と風速、気圧配置、気圧、気温、最低でもこれだけはチェックしましょう。
魚ばかり見て、その魚達が暮らす海を見ないのは論外なのです。

あとはポイントですが、これは内緒にしておきますね。
あと潮流と地形が判れば、アオブダイ、フエダイ、伊勢エビ、タコ、イカ、夜光貝、サザエと、良い獲物が100均のアミや安い手銛で結構捕れます👍
と、厳しい話しましたが、全体で見れば、毎年のように事故は起きてます。
楽しい島暮らしは、安全第一です!!
時化の日に得られた釣果の自慢話に感化されないよう、注意してください‼️
トータルで見たら、安全に正しい漁獲が一番実績あるし、長く楽しめるものです。
それでは皆さん、良いお年を✨
オンリーワン
肌寒くなってきましたね。
体の厚みが人一倍、暑いのより寒いのが得意な、どうもお馴染み、オレンジの僕です。
寒くなるにつれ農繁期も近づいてきます。
さてさてそんな折、今回ご紹介しますのは、世界でもここ徳之島だけ、オンリーワンな陸産貝類(カタツムリのことです。)から一種。
実は、小笠原だけではありません。
ここ徳之島にも、世界自然遺産足る生物多様性を証明する、世界で唯一徳之島だけな固有カタツムリが、実は6種もいることが判ってます(研究途上なので、まだまだ見つかっていない新種もいる可能性は充分に有り)。
そんなみんな大好き固有種カタツムリがこちらです↓↓

トクノシマケマイマイ
そう、種名に徳之島の名を関するカタツムリです。
実はあまり紹介したくありません。
なぜなら、マニアの密猟もあるからです。
だけどこの際はっきり言います❗
実は私、国有林の巡回パトロールも行っております。
ただお茶目なオレンジの太っちょじゃありません。
密猟を見つけたら容赦しません👍
安心してください。すぐ警察に突き出します👋
怖いですよー?
なので、密猟はしない絶対!!
お兄さんとのお約束だよ😉
そんな話はさておき✋
(密猟しないなんて常識です)
このカタツムリもそうですが、実に小さな小さな命です。
こんな小さな命達にも、世界で唯一徳之島だけな世界が広がり、この徳之島を作りあげています。
豊かな自然は島の宝✨
この小さな命達も、森の循環、しいては、川の循環、里の循環、海の循環、すべての循環に寄与しています。
一つ一つの命を大切にしていきたいですね👋✨
みんな一生懸命生きてます。
どうもオレンジの人です。
前回紹介した爬虫類、ハイに続きまして、今回はここ徳之島に自生する食虫植物、コモウセンゴケを紹介します。

このコモウセンゴケ、痩せた土地、陽当たりの悪い土地でも生えることのできる植物なんですが、理由は簡単。
虫を食べて栄養源にできるから✨
彼らは彼らなりに、生きる工夫を見出だし、痩せた土地でも一生懸命逞しく生き、そして自然の循環に寄与しています。

私もこうして、彼らに学ばせてもらいながら、日々楽しく暮らしていきたいと思いますよ🎵
でわでわ。
1 / 2